ネガティブ・ケイパビリティ
作家であり精神科の医師でもある帚木蓬生さんは、ネガティブ・ケイパビリティ(negative capability)について論じた書籍の中で、ネガティブ・ケイパビリティを「直訳すれば『負の能力』『陰性能力』となるが、解釈を一歩発展させて、『どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力』と規定したい」と述べています。
医療の現場における解決できない問題
私たちはこれまで学校や勤め先において、常に「問題を解決する能力」を求められ、「解決を実践する方法」を教わってきました。
医療においても例外ではなく、医療従事者は患者さんの疾患をできる限り早く正確に見つけ出し、治療を施し、元の健康な状態に戻してあげることが正しい道筋であることを疑いません。
そのために、医師は精度の高い検査データを重視し、最良の治療方法を選択します。看護師はベッドの傍らに寄り添って膨大な看護業務を行い、さらには患者さんの良き相談役として彼らの訴えに耳を傾け、それを医師に伝える役割を果たします。その行為のすべてが「問題を解決する」ための手段であり実践となります。
ところが、病気は必ずしも解決できるとは限りません。つまり、どんなに努力をしても「解決できない」事態が少なからず発生してしまうのです。
その時、医療従事者は無力となります。
「これ以上は治療の施しようがありません」
そう宣言をした時点で、医療従事者は、患者さんの前から姿を消すしかないのです。後は、患者さん自身や家族が問題を解決するしか方法がありません。
立ち去らず、共にいる
さて、「問題を解決する」ことだけを学んできた医師や看護師が、解決できない事態に陥ったときは、無念な気持ちを残しながらそこから立ち去るしかできないのでしょうか。
帚木蓬生さんは、次のように語ります。
「遺族を苦しめ続けるものの大部分は、後悔です。『もっと何とかしてやれなかっただろうか』『受診させるのが遅すぎたのではないか』『モルヒネを頼んだので死期を早めたのではないか』と、いくつもの後悔が遺族を苦しめます。どんなに患者さんに尽くした家族でも、死後、『もっとしてやれたのに』と悔やむようです。これはもう間違った認識としか言いようがありません。そんなときには、医師が『あれ以上の介護と献身は、考えられません。主治医である私がよく見て知っています』と言ってあげるだけで、遺族の心の負荷は軽くなります」
医師は立ち去るのではなく、遺族と一緒に「どうにも対処できない事態」に耐え、遺族を「承認する」ことが大切だと説きます。
帚木さんは、さらにこう続けます。
「遺族はまた、周囲から、『新しい気持で前向きにしないとだめよ』と言われ、無理やり悲しみを封じ込まれがちです。こんなときにも、主治医が同じような悲しみに満ちた態度で話を聞き、遺族の回復を辛抱強く待つのは、何よりの助けとなるはずです」
「ペーシング」の手法
医療が目指すのは「問題の解決」すなわち、患者さんの治癒であることは言うまでもありません。
しかし、それが叶わない事態になったとき、「もう、私たちにできることはありません」とその場を立ち去るのではなく、遺族と共に「どうにも対処できない事態に耐えること」も時として必要なのではないのではないでしょうか。
「ペーシング」という「傾聴」の技術があります。
相手と対話をする際、「相手の呼吸」「姿勢」「動き」「声」「話し方」「話す速さ」などを気づかれないように微妙に真似て、相手のペースにこちらが合わせていく方法です。
心が痛んでいる相手に接する時は、できるだけ心の負担にならないような接し方が好ましいという考え方から生み出された技法だと言われています。
医療従事者には、傾聴の型としてこの「ペーシング」の技法を身に付けておくことは大変有効だと考えます。
患者さんや家族あるいは遺族の方は、時に「どうにも対処できない事態」の中で、不安と絶望と諦めの状態にあります。医師もその中に入り、同じ地平で悲しみや不安を共有することが真に患者さんや家族に寄り添うことになるのです。
「不安を感じていらっしゃるのですね」
「痛みは本当に辛いですよね」
このような言葉を、相手と同じトーンで話すことで、不思議と相手の悲しみや苦しみがこちらにも伝わってきて、自然とお互いが「共感」し合うことで相手の悲しみや苦しみが軽減することもあると思います。
医療の目標は、決して「課題を解決する」ことだけではありません。課題を解決することは叶わなかったけれども、医師や看護師が自分たちと同じように「どうにも対処できない事態」を共有してくれたことで、患者さんや家族や遺族は十分に慰謝を得ることができるのです。
(医療コミュニケーション協会 須田)
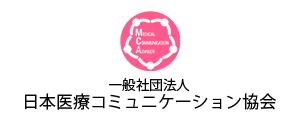




















この記事へのコメントはありません。